Takayuki Oishi
大石 尊之 教授
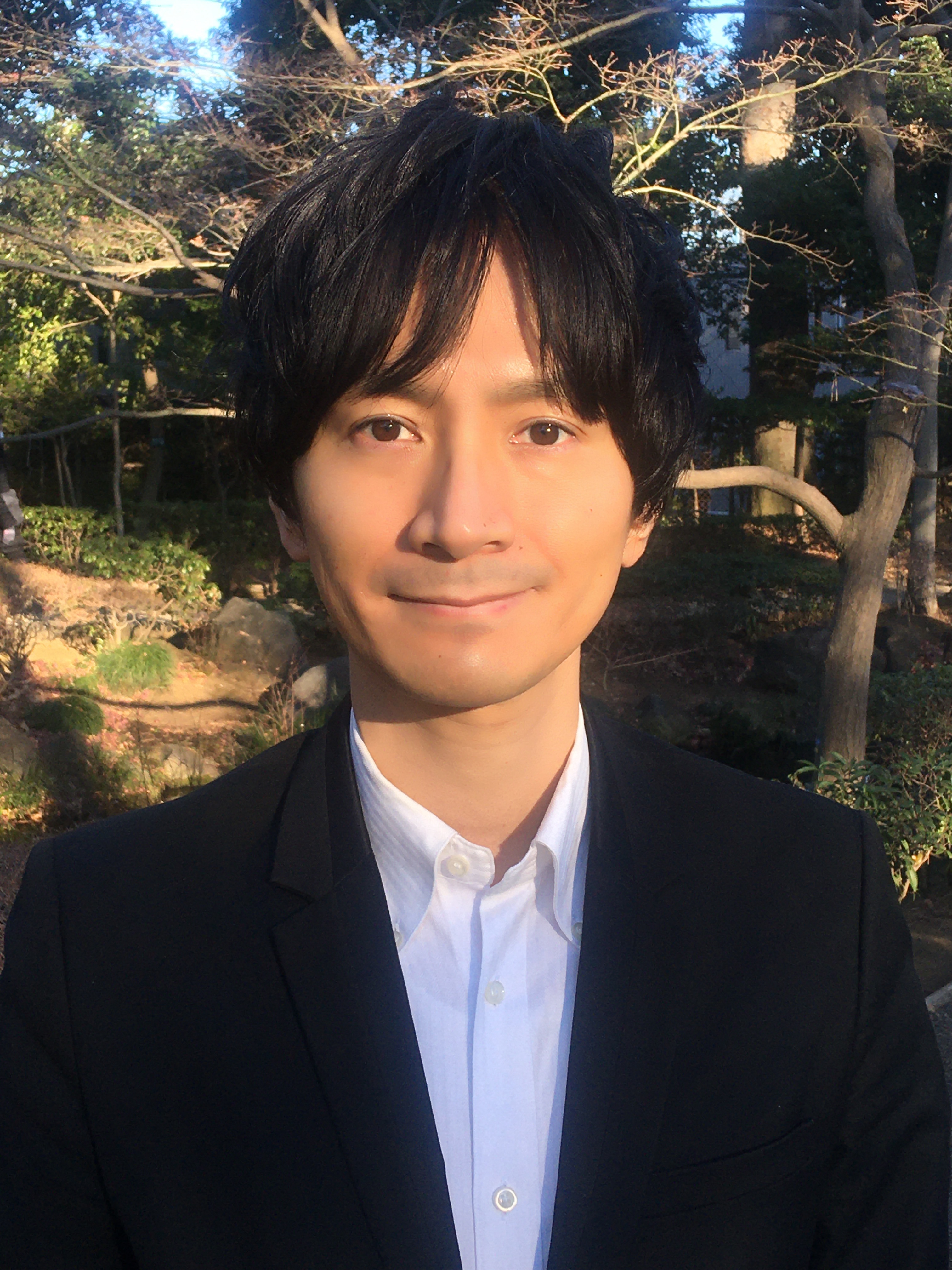
- プロフィール
-
学位博士(経済学)
最終学歴慶應義塾大学 大学院 経済学研究科 博士後期課程修了
専門分野法と経済学、市場と組織の経済学
主要研究テーマ
- 法と経済学の公理的分析およびゲーム論的分析
- 取引費用を伴う仲介市場の経済分析
- ブロックチェーンと所有権の経済分析
主な社会的活動
公益財団法人トラスト未来フォーム 研究会「デジタル時代の所有権と信託:経済学的・比較法的分析に基づく検討に関する研究」 研究委員
(2023年7月1日から2025年6月30日まで)一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会 ハイヤー・タクシー業高齢者雇用推進委員会座長
(2024年4月24日から2026年3月15日まで)
- 主要担当科目
-
法と経済学、ミクロ経済政策、初級ミクロ経済学、ゼミナール
- 所属学会・役職
-
日本経済学会,法と経済学会, Game Theory Society, Society for the Advancement of Economic Theory, The Econometric Society, American Economic Association
- 主要な研究業績
-
- [著書・共著]
大石尊之「仲介取引市場の経済分析」,『市場の質と現代経済』(矢野誠, 古川雄一編著) 第7章 執筆担当(単独), 151-184頁(総260頁), 勁草書房, 2016年. - [学術論文・共著]
Takayuki Oishi, Gerard van der Laan, René van den Brink, Axiomatic analysis of liability problems with rooted-tree networks in tort law, Economic Theory 75, pp.229–258, 2023. - [学術論文・単著]
Oishi, T., A generalization of Peleg’s representation theorem on constant-sum weighted majority games, Economic Theory Bulletin 8, pp.113-123, 2020. - [学術論文・共著]
Oishi, T., Nakayama, M., Hokari, T., Funaki, Y., Duality and anti-duality in TU games applied to solutions, axioms, and axiomatizations, Journal of Mathematical Economics 63, pp.44-53, 2016. - [学術論文・共著]
Oishi, T., Nakayama, M., Anti-dual of economic coalitional TU games, Japanese Economic Review 60, pp.560-566, 2009.
- [著書・共著]
- ゼミナール紹介
-
- 演習のテーマ
-
法と経済学(競争法の経済学)
- 演習の内容
-
学生の皆さんは「法律」と聞くと、六法(憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法)などを思い浮かべるかもしれません。しかし、私たちの日常生活や企業活動を円滑に営むうえで法律が不可欠である、という認識は共通していることでしょう。1960年代以降、主にアメリカで発展してきた「法と経済学」は、各国の主要な法領域を分析対象としており、これまで所有権や財産権、不法行為、契約法、刑法、競争法・知的財産法、さらには国際法まで幅広く研究が行われてきました。
私自身は、市場理論・ゲーム理論・グラフ理論といったミクロ経済学やネットワークに関する数理分析の手法を用いて、因果関係が複雑に絡み合う不法行為法の問題についての公理的分析や、デジタル所有権の形態が市場と法制度の双方を通じてどのように内生的に決定されるのかを経済理論に基づいて研究しています。近年は研究代表者として、「ブロックチェーンの法と経済学:スマートコントラクトの財産権分析」(2024年度科学研究費助成事業 基盤研究(C))や「ブロックチェーンと所有権の経済分析」(2023年度明治学院大学産業経済研究所プロジェクト)などの研究を立ち上げ、学内外の経済学者・法学者とともに研究プラットフォームを構築し、デジタル時代に対応する新しい法制度設計の理論構築を進めています。
私は「法と経済学」を、法制度や法律の社会的パフォーマンスを評価し、また規範や慣習を含む法的ルールが市場や組織とどのように関わるのかを明らかにするための経済学と位置づけています。こうした視点から、これまで3年ゼミでは、規範や慣習のメカニズムを、ゲーム理論を通じて議論するために、海外の法と経済学者によるテキストを輪読してきました。また、「ブロックチェーンと法」に関する海外の法学者による文献も扱い、デジタル技術と法制度の関係について理解を深めてきました。
4年ゼミでは卒業論文執筆に向けて、各自が関心を持つ「法と経済学」関連テーマに基づいて研究を進め、論文指導を行っています。ゼミ生は、私が担当する「法と経済学1・2」を必修として履修し、その過程で基礎的な考え方を身につけます。
2026年度は、ゼミ開講当初に取り上げた村上政博著『独占禁止法 新版―国際標準の競争法へ』を再び題材とします。日本の独占禁止法が禁じる「公正な競争を阻害する行為」とは何か、またデジタル・プラットフォーム事業者による独占禁止法違反事例からどのような競争政策的な含意が導かれるのかを、法と経済学の観点から詳細に検討していきます。
(なお、2026年度はBゼミとして開講予定です。)